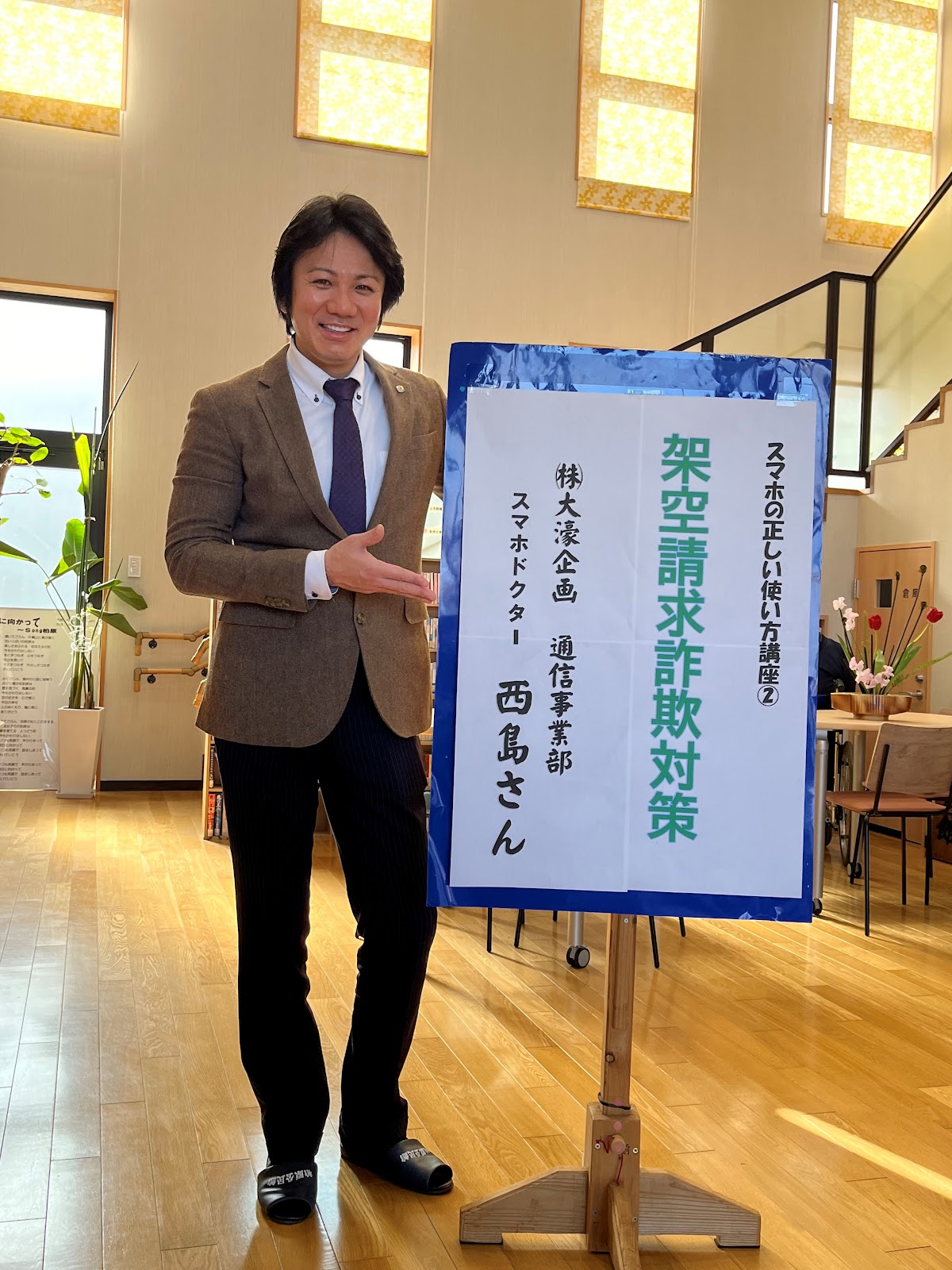年明け最初の『歴史講座』を、1月25日(土)10時より開催しました。
今回は、福大考古学研究室助手の大重優花さんによる「中世の鉄の種類と生産・流通」のお話、そして大学2年生・佐藤萌美さんによる「古代の鉄生産について」のお話をして頂きました。
前者のお話では、「鉄とは何ぞや?」とのテーマで、3つの種類の説明がありました。江戸時代の市場に流通していた鉄は、①アラガネ(荒鉄)・ナベガネ(鍋鉄)・ヅク(生鉄・銑)と呼ばれた『銑(ヅク)』、②ネリガネ(錬・錬鉄)・ヒラガネ(鍱・枚鉄)・ノベガネ(延鉄)・軟鉄・柔鉄などと呼ばれた『熟鉄(じゅくてつ)』、③ハガネ(刃金・鋼・剛)・フケルカネ等と呼ばれた『釼(ツルギ)』の3種に」分かれ、近世では「熟鉄」が「銑」より経済的価値は高かったそうです。
日本国内で製鉄遺跡が確認できるのは、6世紀後半・律令制のときだそうです。11~13世紀頃には、国内の産鉄国は減少し、14世紀以降は中国地方・東北地方に集約・二極化されたとも。それは、律令制下の租税制度により、製鉄技術は全国に拡散したものの、律令制の解体からコスト重視の商品生産を施行した結果、採算性が低い工房は解体され、鉄生産は上記のように集約されたという事です。それ以外の地域では、荘園制的流通システムの下、鋳物師や鉄商人によって、熟鉄や銑鉄が流通したとのこと。しかしながら、国内で日本刀をはじめとした鉄製品の需要が、国産鉄の生産・供給量を上回ったため、中国などからの輸入鉄に頼らざるを得なくなってしまったのではないかと、大重先生はお話しされました。近年、沈没船から引き揚げられた大量の鉄鍋や棒状製鉄品は、倭寇の一部を示すものと思われ、そのことを裏付けることと言えそうです。
後者の「古代の鉄生産」については、鉄は古代日本において最重要資源の一つであるという事で、油山山麓での鉄生産の様相の解明は、日本古代史上においても意義あるものとされているそうです。日本古代における初期製鉄は、砂鉄製鉄に鉄鉱石製鉄が先行しているとのことで、朝鮮半島の古代製鉄遺跡では、主に鉄鉱石が原料として使われており、日本に最初に伝わった製鉄技術は鉄鉱石製鉄であると推定されるそうです。一方で、鉄鉱石製鉄が行われるようになって間もなく、砂鉄製鉄が行われるようになったことも分かっているそうです。
柏原遺跡群では鍛冶炉跡と製鉄炉跡が併せて、24基出土しています。それに加えて、製鉄に関連する遺物として、ふいごやるつぼ、炉壁、鉄滓も見つかっています。炉跡に付属する建物や炉跡を覆うような建物の後も見つかっています。古墳時代から古代にかけて継続していたと考えられるため、大規模なものではないが、集落跡と目される遺跡内から見つかっており、集落に関係する地域から見つかった炉跡としては、数は多いとのこと。また、鉄滓や鉄塊の供献が見られる古墳や、「郷長」「左原補」とある墨書土器、石帯などが見つかっているなど、柏原遺跡群は古墳時代の地方豪族に関する居館や墳墓等であるとされており、出土した鍛冶・製鉄炉跡に関してもこれに関するものと考えられるとのことでした。
熊添がある「西南の杜湖畔公園」周辺は、油山から延びる低丘陵(朝倉丘陵)の上にあって、古代の製鉄炉跡を含む遺跡や古墳が存在しており、製鉄を行った集団が存在していたと考えられるそうです。また、油山山麓には数多くの古代製鉄の様相を物語る遺跡が存在しますが、それら製鉄を行った集団がどのような集団であるのか、製鉄の原料には何を使用したのか等、分かっていないことも多く、今後の研究課題となっているそうです。
【参加者の感想・・・一部抜粋】
●なぜ、油山山麓に古代製鉄遺跡が多いのか?中世製鉄の中国との関連性が新しい視点で考えられました。
●柏原の樹木について、羽黒神社や埴安神社には、大楠など立派な保存樹木があります。柏原には、他にもそういう樹木があるのか知りたいです。また、バス停から園芸公園に向かう道の森の木は、ひこばえが何本も伸びた木があります。なぜそのような木があるのか、歴史と関係があるのか知りたいです。(昔、薪をとるための木だったのでは?と聞いたので)古代製鉄で、柏原にあったなど、近場の歴史に興味を持ちました。ありがとうございました。
●毎回、講座ありがとうございます。いつも学びが多く、有難いです。これからも楽しみです。歴史の上で、福岡(南区この周辺)と中国や韓国との貿易や国交など知りたいです。
●柏原の製鉄は何度もお話を聞いていますが、そのたびに新しい発見があって、面白いです。